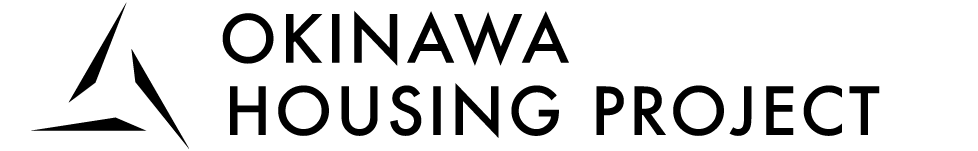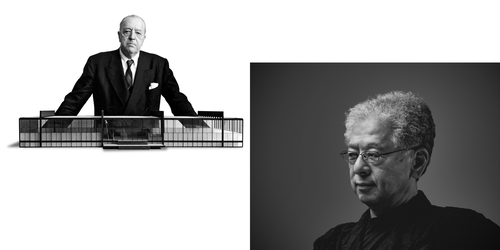沖縄県の地理と行政区分

地理
沖縄県は、日本の南西端に位置する県です。
海域は、南北に約400km、東西に約1,000kmにわたり、本州の3分の2の広さがあります。
沖縄本島を中心に多数の島々が点在し、指定離島は54、外周0.1km以上の島を含めると691に及びます。
沖縄の地形は、サンゴ礁が隆起してできた石灰岩が、独特の景観を作り出しています。
行政区分とエリア
沖縄県は、11市5郡から構成されており、その多くが複数の島にまたがる形で存在します。
一方で、民間や観光ガイドでは、便宜的・慣習的なエリア分けが一般的です。
11市
那覇市 / 宜野湾市 / 石垣市 / 浦添市 / 名護市 / 糸満市 / 沖縄市 / 豊見城市 / うるま市 / 宮古島市 / 南城市
5郡
国頭郡 / 中頭郡 / 島尻郡 / 宮古郡 / 八重山郡
本島北部
国頭郡 / 国頭村 / 大宜味村 / 今帰仁村 / 本部町 / 恩納村 / 宜野座村 / 金武町 / 東村 / 名護市
本島中部
沖縄市 / うるま市 / 宜野湾市 / 浦添市 / 中頭郡 / 北谷町 / 嘉手納町 / 西原町 / 読谷村 / 北中城村 / 中城村
本島南部
那覇市 / 豊見城市 / 糸満市 / 南城市 / 島尻郡 / 与那原町 / 南風原町 / 八重瀬町
離島
本島周辺の離島 / 慶良間諸島 / 久米島・粟国諸島 / 大東諸島 / 宮古列島 / 八重山列島
沖縄県の交通アクセス

那覇空港から本土・海外へのアクセス
那覇空港には、日本とアジアの主要空港への直行便が多数運航しています。
国内線の所要時間は、東京は約2時間30分、大阪は約2時間、名古屋は約2時間、福岡は約1時間45分です。
国際線は、韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポールなど、45都市に就航しています。
沖縄県内の移動手段
飛行機
空路は、短期間で複数の島を巡る際や、遠方の離島へ行く際に便利な交通手段です。
一般的な定期運航便のほか、高級志向やプライベート重視型の小型機チャーターやプライベートジェットもあります。
荒天時は運休・欠航・遅延するケースがあるため、運航状況を事前に確認することが非常に重要です。
車
沖縄県は車社会で、公共交通機関のみで移動できるエリアは限られています。
レンタカーは観光客の最も一般的な移動手段で、那覇空港周辺を中心に多くのレンタカー会社があります。
観光シーズンはレンタカーが不足しやすいため、計画性と事前予約が必要です。
那覇市から中部にかけては慢性的な渋滞が発生するため、朝夕の通勤時間帯は注意が必要です。
タクシー
本土に比べて初乗り運賃が安いため、短距離の移動や複数人での移動に便利です。
配車アプリは、DiDi、GO、Uber Taxi が利用できます。
タクシーがない小さな離島では、事前予約制のツアーやレンタサイクルを利用して周ることができます。
モノレール(ゆいレール)
沖縄都市モノレール線(ゆいレール)は、那覇市と浦添市を走る沖縄県唯一の軌道系交通機関です。
総延長は約17 km、那覇空港駅からてだこ浦西駅までの19駅を結びます。
地上8〜20メートルの高架路線を走り、車窓からは街並みや青い海を一望できます。
県庁前駅、美栄橋駅、おもろまち駅、首里駅など、主要な観光地への移動に最適です。
船
航路は、離島が多い沖縄県で、それぞれの離島が持つ魅力を体験するための重要な交通手段です。
主に、大きな荷物の運搬に最適なフェリーと、短時間で移動できる高速船の2種類があります。
荒天時は運休・欠航・遅延するケースがあるため、運航状況を事前に確認することが非常に重要です。
沖縄県の気候

天気
沖縄県は、亜熱帯海洋性気候に属し、一年を通して温暖かつ多湿です。
梅雨明けから夏にかけては、晴れの日が多い傾向にありますが、スコールと呼ばれるにわか雨がよく降ります。
日差しは強いですが、海風があるので猛暑日になることはほとんどありません。
夏から秋にかけては、台風の接近が非常に多いため、強風や大雨に注意が必要です。
冬は、曇りや雨の日が増える傾向です。
気温
沖縄県の年間平均気温は、2024年時点で24.4℃と、一年を通して温暖な気候です。
最も寒い1月の平均気温は17.9℃で、冬でも暖かく過ごしやすい日が続きます。
最も暑い7月の平均気温は30.5℃で、夏でも35℃以上になる日はほとんどありません。
湿度
年間平均湿度は約70〜80%で、一年を通して湿度が高いです。
最も湿度が高い6月の平均湿度は約83 %で、 特に梅雨の時期や夏は蒸し暑さを感じます。
降水量
年間降水量は約2,000mmを超える地域が多く、日本国内でも多い水準です。
特に、雨が多い梅雨の時期と台風の影響を受けやすい夏は、降水量が多くなります。
冬の月間降水量は約100mmで、最も多い月に比べて半分以下となります。
強風
海に囲まれた沖縄県は、一年を通して風が強い傾向にあります。
春先は、東シナ海で発生した低気圧が沖縄付近を通過する際に、二月風廻り(ニンガチカジマーイ)と呼ばれる強風が吹きます。
梅雨明け直後は、南〜南西の方角から、夏至南風(カーチーベー)と呼ばれる強風が吹きます。
冬季は、東シナ海から沖縄付近にかけて強風が吹きます。
台風
沖縄県は台風の通り道にあり、台風の接近が非常に多い地域です。
台風は年間平均7〜8回ほど接近し、7月から9月は最も多い時期です。
台風の勢力が強い場合、移動速度が遅くなるケースが多く、長時間にわたり大きな影響を受けることがあります。
地震
沖縄県は、本土に比べて地震が少ない傾向にあります。
しかし、沖縄本島近海や宮古島近海を震源とする地震はしばしば発生しています。
2010年の沖縄本島近海地震では、マグニチュード7.2、最大震度5弱を観測しました。
また、地震に伴う津波のリスクも考慮する必要があります。
沖縄県の歴史と文化

琉球王国
琉球王国は、1429年から1879年の450年間、琉球諸島を中心に存在した国家です。
1429年、尚巴志(しょうはし)が三山(北山・中山・南山)を統一したことで、琉球国が成立したと伝えられています。
琉球王国は独自の王国として栄え、中国や東南アジアとの交易を通じて独特の文化を築きました。
しかし、1609年に島津氏による琉球侵攻を受けて、薩摩藩と江戸幕府によって外交権と貿易権に大幅な制限が加えられました。
1879年、明治政府の琉球処分により琉球王国は解体され、沖縄県が設置されました。
第二次世界大戦
1945年の第二次世界大戦末期、沖縄諸島に上陸した米軍と英軍を主体とする連合国軍と日本軍との間で、激しい地上戦(沖縄戦)が行われました。
日本軍の本土防衛のための時間稼ぎという目的で、多くの一般住民が戦闘に巻き込まれ、多くの命が失われました。
1996年、沖縄県生活福祉部が発表した沖縄戦の全戦没者数は200,656人にのぼりました。
(沖縄県出身軍人軍属が28,228人、他都道府県出身兵が65,908人、一般県民が約94,000人、米軍が12,520人)
この悲劇的な出来事は、沖縄の人々の心に深い傷を残し、現在も平和を希求する原点となっています。
本土復帰
第二次世界大戦後、沖縄はアメリカの統治下に置かれました。
本土との行き来にはパスポートが必要になるなど、日本とは異なる政治・経済体制が続いたため、沖縄県民の間で本土復帰を求める声が高まりました。
1972年5月15日、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、本土復帰が実現しました。
伝統芸能
沖縄には、琉球王国時代に発展した独自の芸能が今も受け継がれています。
琉球舞踊は、琉球王国時代に宮廷で踊られていた古典舞踊と、明治以降に庶民の生活を題材にした雑踊(ぞうおどり)からなる舞踊です。
組踊(くみおどり)は、琉球王国時代に中国からの使者を歓待するために創作された歌舞劇です。
三線(さんしん)は、中国福建省の弦楽器「三弦」を原型とする撥弦楽器で、琉球王国を経由して本土に伝わりました。
お祭り
沖縄では、地域ごとに個性豊かなお祭りが存在します。
沖縄のお盆は、旧暦の7月13日から3日間です。
最終日の7月15日には、祖先の霊をあの世へ送り出すために、歌や太鼓に合わせて踊りながら練り歩くエイサーというお祭りが開催されます。
宮古島には、全身に泥を塗った来訪神が、集落を練り歩くことで厄を払うパーントゥがあります。
八重山諸島には、あの世からの使者であるウシュマイ(翁)とンミー(媼)が、集落を練り歩くことで先祖供養を行うアンガマがあります。
沖縄県の食文化と郷土料理

食文化の歴史
沖縄県の食文化は、独特の地理的条件と多様な文化交流によって形成されました。
琉球王国時代に中国との交易で発達した宮廷料理、薩摩藩から取り入れられた日本料理、アメリカ統治時代に根付いたハンバーガーやステーキなど、幅広い食文化が生まれました。
豚食文化
沖縄で豚は、「鳴き声以外は全て食べる」と言われるほど、豚肉を余すところなく利用します。
豚食文化は、琉球王朝時代に中国の歴代王朝の国王を任命する際に派遣した使節の冊封使(さっぽうし)をもてなす宮廷料理として発達し、徐々に庶民へと広まりました。
ラフテー(豚の角煮)、ミミガー(豚の耳)、ソーキそば(豚のあばら肉)、中身汁(豚のモツの吸い物)など、豚肉のあらゆる部位を使用した料理があります。
医食同源の思想
沖縄の食文化には、ぬちぐすい(命の薬)という考え方があり、食事が健康な体を作るという思想が根付いています。
食事は単に空腹を満たすものではなく、活力を与え、体調を整え、病気を予防する薬として捉えられています。
沖縄料理では、ゴーヤーやヨモギなど、栄養価の高い食材が積極的に取り入れられています。
代表的な沖縄料理
| 麺類 | 沖縄そば、ソーキそば、宮古そば |
| ご飯物 | ジューシー、スパムおにぎり、タコライス |
| 揚げ物 | サーターアンダギー、チキアギ、ミミガー |
| 炒め物 | クーブイリチー、ゴーヤーチャンプルー、ソーミンチャンプルー |
| 汁物 | イナムドゥチ、イラブー汁、中身汁 |
| 煮物 | ソーキ、ラフテー、足ティビチ |
| 野菜・海藻 | 海ぶどう、ウンチェー炒め、島らっきょう |
| デザート・菓子 | ちんすこう、紅芋タルト、マンゴープリン |
| ドリンク・酒類 | 泡盛、さんぴん茶、シークヮーサージュース |
沖縄県の観光地とお出かけスポット

沖縄県の国内外旅行者の宿泊者数は、2024年時点で31,275,600人と、全国で5番目に多い状態です。
観光需要の高い沖縄県には、歴史的・文化的施設や自然の名所が数多く存在します。
代表的な観光地とお出かけスポット
| 本島北部 |
|
| 本島中部 |
|
| 本島南部 |
|
| 本島周辺の離島 |
|
| 慶良間諸島 |
|
| 久米島・粟国諸島 |
|
| 大東諸島 |
|
| 宮古列島 |
|
| 八重山列島 |
|